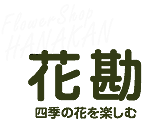 |
||||||
| |
||||||
|
||||||
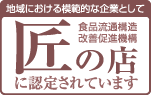 |
||||||
 |
||||||
| 冬のギフト 秋のギフト |
||||||
| 花・フラワーギフトの通 販 埼玉県春日部の花屋 花勘はなかん アレンジメント、花束、プリザーブドフラワー |
| HOME | アレンジ | 花 束 | 鉢 物 | プリザーブド| スタンド | お供え・お悔やみ |
| 知って得する お月見 | ||
| お月見団子 | |||
|
旧暦の8月15日(今年2008年は9月14日)は「十五夜」と呼ばれ、この日は月の見える場所にすすきを飾り、月見団子、お餅、里芋、お神酒を供え、月を見ながら歌を詠み、お酒を飲むという風習がありました。 俗にお月見と言われるこの風習は奈良〜平安時代初期頃より中国から伝わってきたものだと言われています。 <旧暦とは…?> 旧暦とは月の朔望をひと月の単位とし、季節とのズレを閏月で補正した暦です。一般 に言う旧暦とは、これら太陰太陽暦のうちで最後に用いられた天保暦をさして言います。旧暦は月を基準にした暦の数え方のため、旧暦の日付の月は常に決まった形をしています。そのため9月21日は必ず満月だったのです。 <十五夜と十三夜> 昔から日本人は月に対しての思い入れがあり、特にお月見の満月は「中秋の名月」などと呼ばれ最も美しい月とされてきました。ですがお月見はこの日一日限りではなく、実は旧暦の9月13日(今年2002年は10月18日)にも「後の月」「十三夜」などと呼ばれる日があり、「十五夜」にだけ月見をして「十三夜」に月を見ないのは「片見月」と呼ばれ、良くないことだと言われています。 <お月見の起源> 月見は元々は中国の「中秋節」が起源とされ、中国ではこの日に月餅を食べていたのですが、日本に伝わるときはただのお餅に変わってしまいました。中国から伝わったお月見は秋の収穫祭と重なって発展し、秋に収穫される里芋を供えることから「芋名月」とも呼ばれます。また「十三夜」は日本だけの風習で中国には元々無かった日本独自の風習です。「十三夜」には、豆や栗を供える風習があり「豆名月」「栗名月」とも呼ばれています。 お月見に添えたススキは、お月見が終わった後に、すぐに捨てたりしない風習があります。お月見が終わった後は、ススキを庭に差したり、小屋、門、水田に差したりします。ススキには、魔よけになるという俗信があるからです。 |  |
||
| 知って得する 敬老の日 | ||
| 敬老の日 | |||
| 9月第一月曜日の次の日曜日の敬老の日は、聖徳太子が現在の大阪市に悲田院を設立したと伝えられる日に由来しています。この悲田院は、身寄りのない老人や病院を収容する救護施設でした。現在の敬老の日は、1954年に『としよりの日』として設けられたのがはじまりです。この呼び方に異議が起こって、1966年に『敬老の日』と改められて、国民の祝日となったようです。この日から、『老人保険福祉週間』(9月15日〜21日)が始まりました。アメリカでは1978年から、祝祭日になっています。敬老の日以外にも長寿を祝う年があります。数えで61歳(満60歳)になる誕生日の『還暦』から祝うのが習わしとされています。60歳は人生の上で、五回目の年男や年女になる年です。生まれた干支にかえって赤ちゃんに戻るという意味あいで、『赤いちゃんちゃんこ』と『頭巾』を贈るというのがもとの『しきたり』でした。 | |||
| 知って得する 神事 | ||||
|
||||
|
||||
 |
 |
|||
 |
 |
|||
できあがり! |
||||
| 知って得する 七夕 | |||
| あなたは七夕伝説を知っていますか? | |||
| むかしむかし、天の川の西には織姫が、東には牛飼いの彦星が住んでおりました。二人は恋仲になったのですが、一緒にいると仕事が進まなかったため、怒った天帝は再び二人を天の川の両岸に遠ざけてしまいました。
彦星に会えなくなった織姫は嘆き悲しみました。それを見て可哀想に思った天帝は、一年に一度、7月7日だけ、天の川を渡って二人が逢うことを許したのです。でも、7月7日が雨になると天の川を渡れず、来年まで会えなくなってしまいます。するとそこへカササギの群れが飛んできて、天の川に橋を架けてくれたので、雨の日でも二人は逢うことができました。 ところがある時、二人の住む場所が、大変な災害に見舞われました。いつまでもこの土地に住めない、と感じた彦星は、新しい土地を探す旅に出ようと考えました。それまでも一年に一回しか会えなかったのに、旅に出るとさらに長い間会えなくなってしまいます。それでも皆のためと、織姫は笑顔で彦星を送り出しました。カササギの群れが彦星を導き、彦星は天の川から旅立っていきました。 だから今見える彦星は、天の川と反対側の寂しいところにいます。でも織姫は、また会える時を信じて、遠くにいる彦星にも見えるようひときわ明るく輝いているのです。 一年に一度、願いを笹に託す七夕にはこんな物語があったんですね。。みなさんの願い事が 叶いますように。。。 |
 |
||
| 知って得する お盆 | ||
| お盆の迎え方 | |||
| [特別な新盆] 故人の四十九日の忌明け後、初めて迎える御盆を「新盆=ニイボン」といいます。(※四十九日の忌明けより前に、御盆を迎えた時は、その年でなく、翌年のお盆が新盆となります。) 仏壇の前に盆棚=精霊棚を設け、初物の農作物でつくったお供物(きゅうり・なす)を飾り、供養膳に精進料理を盛り、白玉 ・だんご・果物・故人の好物なども供えます。なお、このお供物は墓前にも供えるので、用意します。 また、御盆の間は精霊に自分の家を教えるために、仏壇のそばとか軒先に新盆提灯を飾るものとされています。 御盆の期間 8月13日〜16日 13日〜 精霊棚を飾り、迎え火を焚く 16日 送り火を焚いてご先祖様を送り出します。 |
 |
||
| [精霊棚の飾り方] | |||
| オガラ | ご先祖様をおむかえする時、送る時に家の門で焚くもの。また牛・馬をナス・キュウリでつくる時に足として使ったり、精霊棚用のハシとしても使います。 | ||
| 蓮の花セット | 蓮の花・実・巻葉を飾る。 | ||
| 牛・馬 | ご先祖様の乗り物。いらっしゃる時は馬に乗ってなるべく早くきてもらい、お帰りは牛に乗って、ゆっくりと帰ってもらいます。※お迎えの時は、牛・馬の頭を内側に向け、送るときは外側に向けて飾ります。 | ||
| ほおずき | おむかえする門を明るくする提灯の役目をします。 | ||
| 笹 | ご先祖様の入ってくる門です。笹で門をつくり、ほおずきをぶらさげてください。 | ||
| 盆花 | 造花の蓮です。金・銀は新盆用。赤色は、新盆以外で使います。 | ||
| 現在では、古来からの飾り方に縛られず、、牛と馬も、ナスとキュウリでつくったものではなく、飾っている間も腐敗のない、ワラで作られたものを飾ったりと臨機応変に現代の飾り方へと変化していっています。 | |||
| 知って得する 節分 | ||
| どうして節分には豆をまくの?? | |||
| 節分の日は、「鬼は外、福は内」といいながら豆をまきますが、これは災いをもたらす「鬼」を
硬い豆でやっつけて追い払っちゃおうということです。 「鬼門」って聞いたことありませんか?この「鬼門」は風水や家相などでよく使われる言葉で 十二支でいうと「丑寅」うしとらの方角。北東の方位のことを鬼門をいいます。 鬼門は鬼が出入りする場所として、昔から嫌われているのです。 「丑寅」うしとら。。。節分に出てくる鬼って、牛の角があって、虎のパンツはいてませんか? 節分の鬼のイメージって、その方角の「丑寅」からきているんですよ。おもしろいですよね。。 そこで、季節の変わり目の節分の時期に、鬼門に向かって「鬼は外〜!福は内〜!」 と叫んで鬼を退治し、その退治した豆を歳の数分だけ食べると、無事に春を迎えられると 言われています。 |
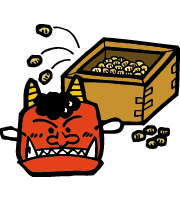 |
||
| 節分にヒイラギを飾るのはなぜ? | |||
| 鬼の目にヒイラギの葉が刺さり、痛がって逃げると言われています。節分の豆を蒔いて、 ヒイラギの葉を飾れば、ほぼ完璧です! |  |
||
| 節分に巻き寿司を食べるのってなぜ? | |||
| 節分には、その年の恵方に向かって巻きずしをまるかぶりするという風習があります。
ちなみに2008年は南南東です。 巻きずしは、海苔で太巻きで中にはたくさんの具・・・・
たくさんの福を1本に巻き込むところからきています。 恵方に向かって黙って食べるのは、「福」がウチから逃げてしますので、一切しゃべらずに、 食べなければいけないのです。 またまるごと食べる理由は、たくさんの福と縁をきらないように包丁を入れない。。という 事からだそうです。 |
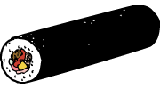 |
||
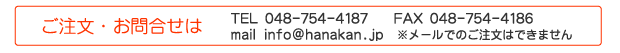 |
||